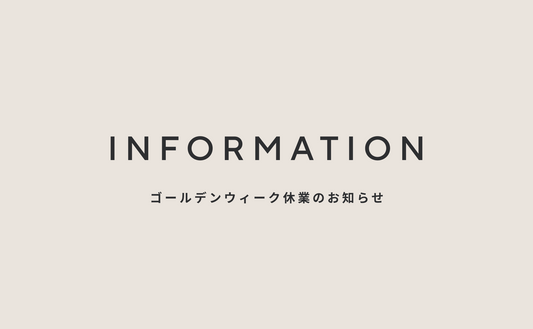本コラムでは、昨今話題になっている「キーボードのデッドゾーン」について、ZENAIM開発チームの考え、そしてZENAIM KEYBOARDにおける設計と、今後の改良方針についてをご紹介します。
本コラムは、以下2章で構成されています。
①なぜ「デッドゾーン」は必要なのか?
②応答性と安定性の両立を追求するため、ZENAIMが必要としたのが“0.2mmのデッドゾーン”
※「ZENAIMキースイッチの前提情報から知りたい」という方は、まずはスイッチに関するコラムをご覧ください。
①なぜ「デッドゾーン」は必要なのか?
ここ最近、高性能な磁気検知のキーボードが増えてきていることで、デッドゾーンの有無やその度合いがコアなユーザー間での関心毎になっています。
例えば、ゲーム中にキー操作をしたのに、直感的にキャラクターが動かないことって、ありませんか?その原因のひとつがデッドゾーンです。
デッドゾーンという言葉についてZENAIM開発チームでは、磁気検知式スイッチにおけるキーストロークのはじまりとおわりにあるキーが反応しない区間と捉えています。
一般的なスイッチの構成部品は4~6点ほどあり、それぞれの部品にはコンマ数mm程度の製造ばらつきがあります。それらを組み立てて作られているスイッチの多くは、軸のガタやストロークにおよそ0.05mm以上の個体差を持つことになります。
さらに、磁石は温度によりその磁力が変わることから、夏場や冬場などの温度差により、1mm以上もの誤差につながる可能性があります。
キーボードはこれら製造上のばらつき、環境要因のばらつきを加味して、ソフトウェア制御で安定した性能を実現する必要があります。
デッドゾーンは、ストロークのはじまりとおわりに反応しない区間を設けることで、ばらつきに対する安定性を確保している区間、と考えられます。
デッドゾーンを0にすることは技術的に可能ですが、ZENAIMは誤動作を前提にして応答性を高めてはいけないと考えており、その理由を後述します。
まず、なぜこのデッドゾーンは必要なのでしょうか?それは磁気検知式スイッチのストローク判定の仕組みに起因します。詳しく見ていきましょう。
磁気検知スイッチの仕組みは、以下3つの手順で成り立っています。
1. スイッチのステムに装着された磁石に対し、基板に実装されたホールセンサICが磁力を検知し、電圧に変換する
2. ステムのストロークに応じて変化する電圧値をMCUでデジタル変換し、計算式に基づいてストローク量を算出する
3. 算出したストローク値に対し、アクチュエーションポイント、リセットポイントの判定を行い、USB通信でPCに情報を伝達する

ここで重要なのは、「磁力の変化を縦方向のストロークという一つの直線上の値に変換している」ということです。
スイッチ自体は縦方向にしかストロークしないものですが、スムーズなストロークを実現するために「ステム」と「ガイド」にはわずかなすき間が設定されています。
すき間がゼロになると、ステムはストロークができなくなってしまいます。一方、すき間がわずかでもあれば、ステムはガイドの中で傾くことができます。
この傾きにより磁力がわずかに変化すると、高精度なセンサーであるほど電圧がセンシティブに変動します。その結果、ストロークをさせたつもりがなくても、システムは「ストロークをした」という判定をしてしまうことになります。
つまり、『「傾いていること」と「ストロークしていること」を分けて判定することができない、その現実をどう処理するか?』、これがデッドゾーン議論の技術的な背景になります。
まっすぐ正確にスイッチを操作する場合は、高い精度でストローク判定ができるのですが、例えばスイッチの端を押さえて長押ししている状態でわずかに傾きが生まれると、「ストロークが戻った」という判定がされ、長押しの入力状態が切れてしまうことになります。
FPSゲームなどでの具体的シチュエーションでは、小指でSHIFTやCTRLなどを押している状態で、しゃがみやダッシュなどが解除されてしまうといったケースが考えられます。
そのため、特にストロークの終わり付近の「ボトムデッドゾーン」が注目されているのだと思います。
これらの競技上のリスクに対し、ZENAIMはデッドゾーンを設定しています。

②応答性と安定性の両立を追求するため、ZENAIMが必要としたのが“0.2mmのデッドゾーン”
こういった原理的な理由から、ZENAIM開発チームでは「デッドゾーン0でいかなるときも絶対に誤作動しないキーボードは存在しない」という見解を持っています。
そして、反応速度と耐誤爆性の両立を目指すZENAIMとしては「これはデッドゾーンではなく、セーフティゾーンと呼ぶべきものなのではないか」と考えています。
実は「デッドゾーンなし」という設定自体は、技術的には可能なので試してみたことはあるんです。ただ、これまで述べたように、ごくわずかにキーキャップに触れるだけでオンしてしまったり、押し続けているつもりでも意図せずオフしてしまったりということが起きてしまいます。
温度による磁気変化の影響は、ZENAIM KEYBOARDの「温度補正機能」により解消できています。しかし、キーキャップの微妙な傾きすらセンサーは正確に拾ってしまいます。さらには、スイッチ部品のモノづくり上のばらつき、それを組み付けた時の部品ばらつきの組み合わせがスイッチ毎にかならず変わってくるのも事実です。ごくわずかだとしても、微妙な個体差はある、ということです。
現時点でZENAIMが「セーフティゾーン」と考えるデッドゾーンの目安は0.2mmです。これは軸が傾くことでストロークをさせたつもりがないのに、センサがストロークしたと認識してしまう可能性に対し、誤爆を回避するための余裕しろです。
デッドゾーンを0に近づけるにしたがって、ごくわずかな軸ぶれによる磁石の傾きの影響は大きくなります。
ZENAIM KEYSWITCHは温度などの仕様環境を考慮したうえで、ガタをギリギリまで詰めていますが、それでも完全なゼロにすることはできません。こちらの詳細な説明はスイッチのコラムに譲りますが、ガタをゼロにすると、スイッチはストロークできなくなってしまいます。
現在、このわずかなガタに対するセンシングの余裕しろ、つまり0.2㎜程度みているデッドゾーンを短縮するためのデータ取りと分析を終え、ファームウェアの最終テスト段階に入っています。これが「ZENAIM KEYBOARDはまだソフトウェアで進化できる余地がある」、と謳っている部分になります。
慎重に進めているのは、磁石の傾きだけでなく、温度補正への影響など、トータルで安定させる必要があるためなのですが、何よりZENAIM KEYBOARDの原点といえる「反応速度と対誤爆性の両立」ここをいかに高いレベルで実現するか、が重要であると考えているためです。
先ほどの繰り返しになってしまうのですが、実際デッドゾーンなしという設定は試験的に動かしてみたことはあります。ただ、これまで述べてきたように、ごくわずかな軸ぶれでオンしてしまったり、意図せずオフしてしまったりということが起きることも検証から分かっています。
デッドゾーンなし、アクチュエーションポイントを0.05mmにすると、キーキャップの表面を優しく撫でるだけで、まるで静電タッチパッドのように反応します。0.05mmというのは、コピー用紙の厚さや髪の毛一本分くらいの厚みといえばイメージしやすいでしょうか。
「この感度って、インゲームでは逆に良くないんじゃないか?」と思うのですが、皆さんいかがでしょうか?もちろん、使いこなせたら最強だと思いますが、人類の手に余るのでは...…とすら思っています。
現在、安定性が抜群という評価を頂いており、誤ONやONし続ける現象がないのは、様々なばらつきの要因を吸収できるようにしている証だと考えています。
とはいえ、デッドゾーンが短いものが市場で望まれていることは理解しており、安定動作を保証できるギリギリのラインを0.1mmとしたデッドゾーン短縮のアップデートを予定しております。
引き続き、プロシーンで通用する、突き抜けた機能性を追求していきますので、近日中のアップデートをどうか楽しみにお待ちください!
前提となるZENAIM KEY SWITCHの構造については、下記の記事をご覧ください。
ストローク1.9mmを限りなくスムーズでまっすぐに。理想のゲーム体験を追求したZENAIMの3つの独自テクノロジー